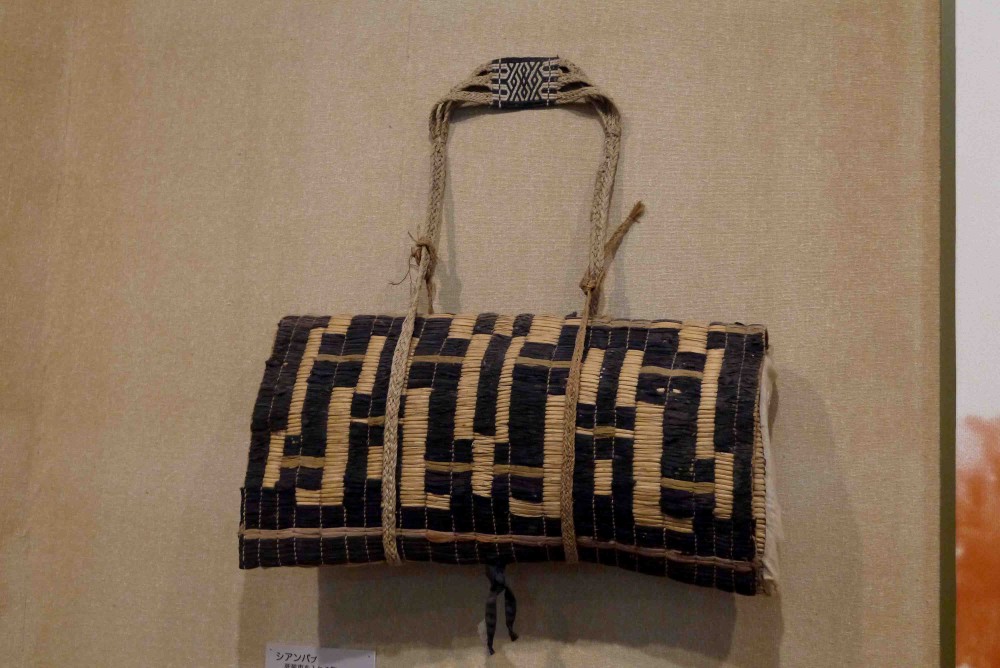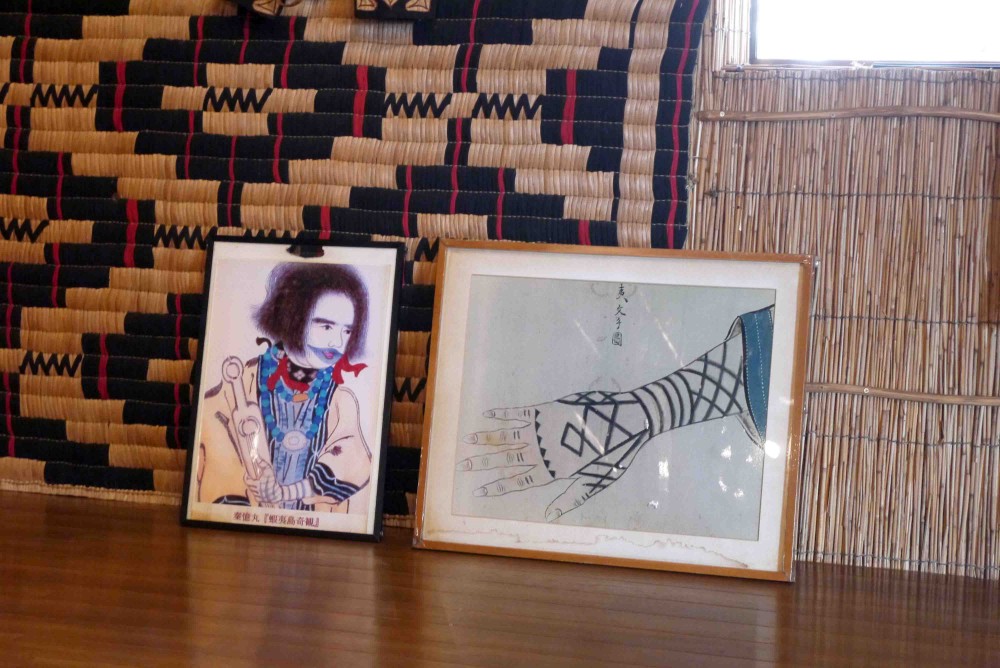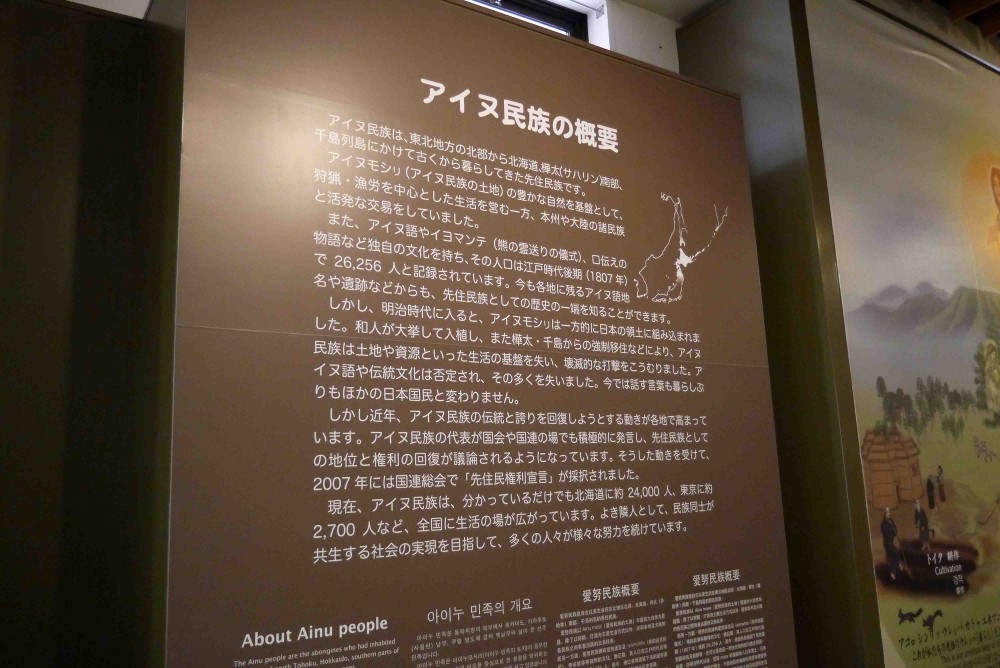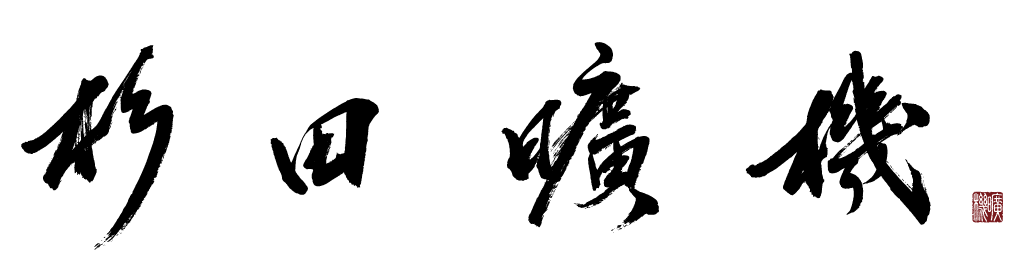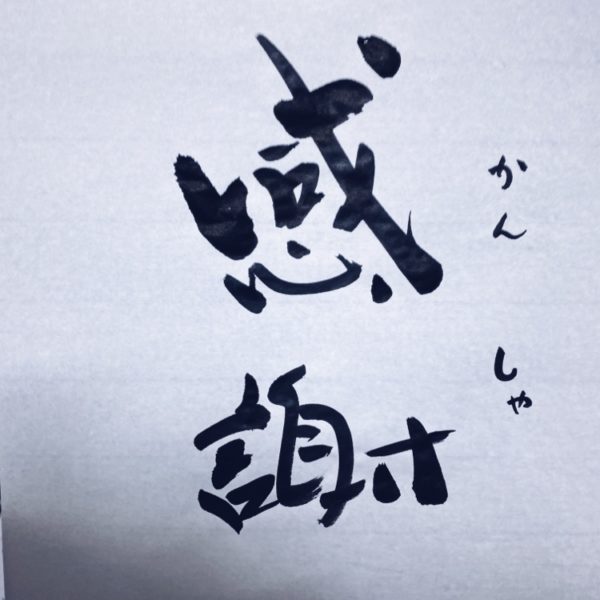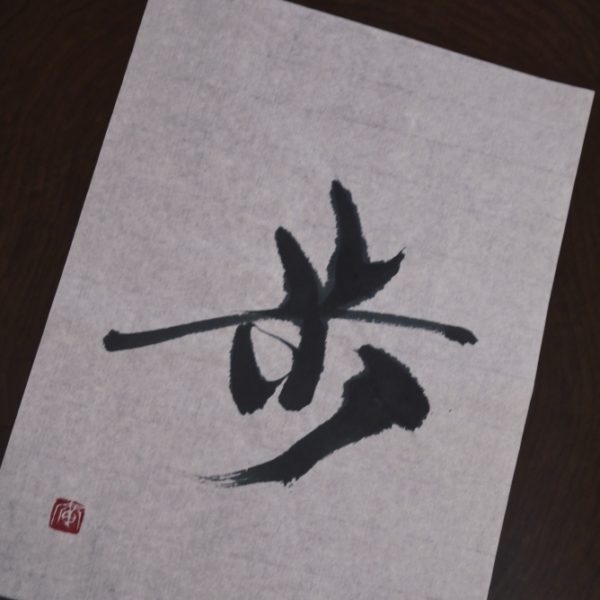3/7に行ったアイヌの町「白老町、ポロトコタン」
2020年には、ここに国立博物館ができるとのこと。
北海道に行ったら、必ず行きたかった場所。
それがアイヌの町。
小学生の時から行きたかった場所。
どこ行きたい?と聞かれて、真っ先に「アイヌの町!」と答えました。
きっと昔、何かしらの縁があったところだろう。
彼らの神事を見ていると、心が震えるものがあり、涙が溢れそうになった。
やっと会えたという気持ちももちろんあって。
周りに気付かれないように涙を潤わせた。
昨年、考古学(人類学)の仕事をされている山口の松下さんと話していて、
縄文時代や弥生時代の人の流れや、
縄文の骨格の話などを聞いていたため、
そうした部分も学びたくアイヌ民族の集落や博物館をみていた。
精神性は縄文のそれを似ていて、神道の基礎とも近いものを感じた。
自然の中に神が宿る。
アミニズムというほうが分かりやすいと思う。
命の考え方など、日本のもつ根幹の「和」の心が、こうした縄文から紡がれているものだと思える。
だから縄文が好きなんだなと思えた。
北海道でここを学べた事が、とても重要な体験だった。
自分の中の古い核がハマったような。
そんな感覚。
武士道や道がつくものも好きだけど、
縄文の精神性を求めていると腑に落ちた。
ここはすごく重要で、これからの制作等にいい刺激になる。
和する、和える、和み、にこにこ(和々)、などなど。
そうかぁと、気付かせられる出会いだった。
ここさえ分かっていれば、
世界中どこへ行っても、
自分は「和」で在れるんだなとも思えた。
和とは強制するものでもない。
着物を着ることだけが和ではない。
茶道や書道、剣道だけが和ではない。
もっと奥深いところに「和」がある。
その答えは日常に溶け込んでいて、それを表現していこうとしていたんだなと気付くことも出来た。
さぁて、どうしようか。
これからを。